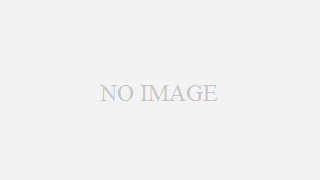「悪いことをしたんだから、罰を与えて当然だ!」
私たちは、何か問題が起こると、
反射的にそう考えてしまいがちです。
物を壊したなら弁償させる、
ルールを破ったなら叱責する。
金銭的な償いや一時的な抑止力にはなるかもしれませんが、
それで本当に問題は解決するのでしょうか?
「悪い」というレッテルが本質を見えなくする
そもそも、物事に絶対的な「良い」「悪い」など存在するのでしょうか?
多くの場合、それは私たちの主観的な解釈に過ぎません。
一つの出来事にも、良い側面と悪い側面が共存していることだってあります。
何か問題が起きた時、
それを「悪いこと」と断定し、
罰を与えるという発想に囚われると、
私たちはその奥にある本当の原因を見落としてしまいます。
例えば、物を壊した人がいたとします。
弁償させることは一つの解決策かもしれませんが、
なぜその人は物を壊してしまったのでしょうか?
不注意だったのか、ストレスが溜まっていたのか、
あるいは何かを訴えたかったのか?
表面的な行動だけを見て罰を与えても、
根本的な原因が解消されない限り、
同じような問題が繰り返される可能性は高いでしょう。
正義感という名の「罰」がエスカレートを招く
さらに厄介なのは、
「悪いことをしたのだから、反省させるべきだ」
「二度としないように厳しく罰を与えなければ」という、
私たちの根底にある正義感です。
謝罪を求めたり、土下座を強要したり、
徹底的に追い詰めたり。
一見、それで相手が改心するように見えるかもしれませんが、
実際には反発を招いたり、行為がエスカレートしたりするケースも少なくありません。
これは子育てにおいても同様です。
友達に暴力を振るう子供に対して、
叱ったり怒鳴ったり、もうしないように諭したり、
ましてや暗い部屋に閉じ込めるといった罰を与えて、
表面的な行動を抑止することはできても、
その暴力の根源にある問題は何も解決しません。
まるで脂肪吸引をしても、
食生活を改めなければリバウンドしてしまうのと同じです。
問題行動の奥にある、満たされない自己
では、なぜ人は問題行動を起こしてしまうのでしょうか?
多くの場合、その行動の裏には、本人も自覚できていない、満たされない何かが存在します。
言葉にできない不安、
認められたいという欲求(自分で自分の欲求を満たすことをOKとしない)
理解してもらえない孤独感…。
特に、「嘘の自分」を演じている場合、
問題は深刻化します。
本当の自分の気持ちを
無自覚に自分で抑え込むと、
心の中で不満や怒りが蓄積し、
いつ爆発してもおかしくありませんよね。
罰ではなく、「なぜ?」という視点
先ほどは子供の例でお話しましたが
これを大人もやっている。無自覚に。ということです。
自覚がないから改善できないという側面もあるのが
この問題の厄介なところですが、
問題行動を繰り返す人に必要なのは、
一方的な罰ではありません。
大切なのは、「なぜ、そのような行動をしてしまうのか」という視点を持つことです。
その行動の奥にある感情や欲求に目を向け、
理解しようと努めること。
本人が言語化できないのであれば、
周りの人が辛抱強く寄り添い、対話を試みることが重要です。
自分を大切にすることから始まる変化
問題行動の根源にあるのは、
多くの場合、「自分で自分を大切にできていない」という状態です。
嘘の自分を演じ、
本当の欲求を無視し続けていると、
心はSOSを発信します。
それが、周りから見ると問題行動として映るのです。
だからこそ、解決の糸口は、罰を与えることではなく、
その人自身が「本当の自分」に気づき、自分を大切にすることをサポートすることにあります。
表面的な行動に目を向けるのではなく、
その奥にある心の叫びに耳を傾ける。
それこそが、問題を根本的に解決し、
より良い関係性を築くための、唯一の道なのです。