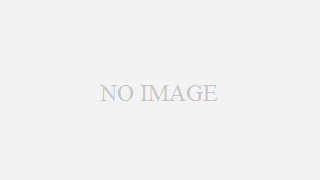「伝え方が大切」コミュニケーションに関する本を開けば必ずと言っていいほど書かれているこの言葉。頭では理解できても、実践しようとすると次第に面倒くさくなる。それは、多くの人がこの言葉を表面的なテクニックとして捉え、心の底から納得できていないからではないでしょうか。
人間の意識は、わずか5%の顕在意識と、95%もの潜在意識で構成されています。頭で「伝え方に気をつけよう」と意識しても、95%の潜在意識が納得していなければ、行動はなかなか変わりません。習慣化できず、結果として現実も変わらないのです。
では、どうすれば「伝え方が大切」ということを、頭だけでなく心で理解し、「腑に落ちる」ことができるのでしょうか?
「価値観の押し付け」では変われない
「伝え方に気をつけた方がいいよ」と誰かに言われたとしても、それは単なる価値観の押し付けに過ぎません。押し付けられた価値観は、私たちの行動を本質的に変えることは難しいでしょう。
だからこそ、私たちは自分自身で「腑に落ちる」必要があるのです。
私が「伝え方」の大切さに腑に落ちた理由
私自身の人間関係における根本的な願いは、「周りの人たちと一緒に、自分もその人たちもみんな幸せになる」ということです。時に厳しいことを言う必要があったとしても、基本的にはどんな人の考え方も否定せず、その人がその人らしく生きることを尊重したいと考えています。
仕事の場面では、どうしても注意や指導が必要な時があります。「できていない」と頭ごなしに怒るのと、相手の気持ちに配慮しながら伝えるのでは、結果は大きく異なります。
しかし、他人に配慮しようとすると、自分の本心とズレてしまうこともあります。相手を気遣うあまり、自分の考えを引っ込めたり、否定してしまう。これは自分を大切にしていない状態であり、いずれ反動がきて、今度はストレートにきつい言葉をぶつけてしまい、人間関係をこじらせてしまう。
「言い方は大事にしたいけれど、そうすると自分の思っていることが言えなくなる」——これは、私も経験してきた葛藤です。
感情の肯定と理性的な目的の融合
この葛藤を乗り越え、私が「伝え方」の大切さに深く納得できたのは、以下のプロセスを経たからです。
- 感情の全肯定: どんな感情であっても、まずは「そう思ったんだね」「そうだよね」と、頭ごなしに否定せず、100%自分で受け入れます。たとえ泥臭く、ブラックな感情だとしても、客観的に一歩引いた視点から、もう一人の自分を慰めるような感覚です。
- 人生の目的を理性的に思考: 自分の感情を受け止めた上で、「人間って何のために生きているんだっけ?」「自分の幸せってなんだろう?」と、理性的に考えます。
- 目的達成のための最適な手段を考える: 自分の人生の目的を達成するためには、人間関係は良好である方が良い。仕事は一人ではできないし、みんなに協力してもらった方がスムーズに進む。みんなと楽しく仕事ができる方が、自分自身の幸福にも繋がる。そう考えた時、「では、自分はどのような行動や発言を選択するのが良いのだろうか?」と自問自答します。
「ふざけんな!どうしてこんなこともできないんだ!?」と怒鳴ることが、本当に自分の目的達成に繋がるのか? それよりも、言うべきことは言いながらも、「いつもありがとう」「あなたの気持ちはわかるよ」「忙しい中、大変だよね」と感謝や共感を伝え、その上で「でも、ここはこうしてほしいんだよね」と丁寧に伝える方が、最終的に良い結果を生むのではないか?
遠回りこそが「腑に落ちる」近道
これは、単に「伝え方を気をつけよう」という表面的なアドバイスを、自分が心から納得するために、細かく分解し、論理的に説明するプロセスです。
この道筋を辿ることで、「伝え方に気をつけた方が良い」という結論に、疑いようのない形で辿り着きます。まるで、複雑なパズルを一つ一つ丁寧に組み上げていくように。
この「疑いようのない」状態こそが、「腑に落ちる」ということなのではないでしょうか。そして、「腑に落ちた」ことは、意識せずとも自然と行動に現れます。それは、わざわざ潜在意識を書き換えようとするのではなく、論理的な思考によって疑いの余地をなくした結果、潜在意識が自然と変化したような感覚です。
表面的な知識や流行に流されるのではなく、自分の感情と人生の目的を深く理解し、論理的に思考することで、私たちは初めて「伝え方」の本質を理解し、行動に移すことができるのです。このプロセスこそが、「腑に落ちる」ための、少し遠回りにも見えるかもしれませんが、実は最も確実な近道なのかもしれません。