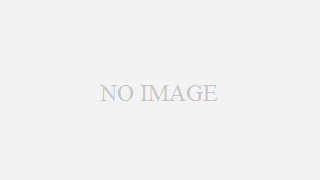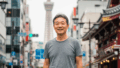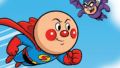私たちは、日々さまざまな場面で、自分はちがう価値観に巡り合います。
そのときに、「自分の経験から、それはそう考えるとうまくいかないんだよな・・・」と
相手の考えを無自覚にジャッジしてしまいます。
ただ、これが前提になると
共感するときに、「わざわざ共感」しなければならなくなります。
そして、しばしば、とりつくろって共感した自分を責めてしまいます。
もっと心から相手のことを理解してあげられたらいいのにな・・・
わざわざ演じない自分になりたいと・・・
「乗り越えたから」というジャッジの罠
人はレベルアップすると
以前までの考え方に縛られなくなるので
物事を俯瞰して見られるようになります。
そのときに、
まだ俯瞰して見れない人を見ると、
「確かにその考えはわかるけど、それをやっているとうまくいかないんだよな。」と感じ
無自覚に「その考えは間違っている」と、他者をジャッジしてしまいます。
「俺もそうだったけど、それを乗り越えてきたんだ」
――この言葉の裏には、「君も努力すればできるはずだ」「私の時はこうだったのに」という、無意識の期待や押し付けが含まれてしまうことがあります。
自分が乗り越えた経験は、確かに貴重な資産です。
しかし、その経験が「正解」や「基準」となり、
現在苦しんでいる他者の「弱さ」を、あたかも「間違い」であるかのように見てしまう。
※正しい方向に導かなければならないという正義感という名のお節介
これは、せっかく苦難を乗り越え、強くなったはずの自分が、
かえって他者との間に壁を作ってしまう原因になりかねません。
弱さを受け入れることが、真の優しさとなる
そうではなくて、本当に大切なのは、
自分が成長したときに、その時の自分の弱さを十分に受け入れることです。
- 「あの時、自分は本当に無力だと感じていたな」
- 「あの状況では、どうしようもなかったな」
- 「あの時の自分は、こう感じるしかなかったんだな」
このように、乗り越えたからといって、
過去の自分の弱さや感情を否定する(だからダメだったんだ・・・)のではなく、
「そうだよね、そんなこともあったよね」と(ダメだった自分、弱い自分)を受け入れる事です。
(これが自己受容)
この自己理解と自己受容のプロセスこそが、
他者を理解する上での「真の共感」を生み出します。
なぜなら、自分の弱さを受け入れた人は、他者の弱さに対してもより寛容になれるからです。
自分はもうクリアしたから、こう考えればいいというのは共感が生まれません。
自分のそのときの弱さを十分に受け止める過程があるからこそ
他者に対しても心からの「そうだよね」が生まれるのです。
クリアしたから関係ない
俺は乗り越えられただと、この弱さを受け止めるというのがありません。
確かに人間として成長はしたけど、
そのときの弱さを受け止めることができていないので、
ジャッジするしかなくなるのです。
変わって良かった、成長できて良かったではなく
そのときの自分の弱さを十分に受け入れることもできているから
わざわざ共感しようとしなくても
自分の経験を相手の苦しみに重ね合わせ、
心から「うんうん、わかるよ」と頷けるようになります。
それは、表面的な共感のテクニックを超えた、人間としての深い優しさです。
自分の弱さを受け入れ、その全てを肯定することで、
私たちは他者の不完全さをも包み込めるような、
真の包容力を手に入れることができるのです。
自分と向き合うことは
自分の弱さを受け入れる事であり
弱さを受け入れる事とは、「そうだよね」と過去の自分に共感(これを癒すという人もいる)していくことであります。
そして、それが大切なのは、
今はもう成長したから、そのときの自分なんて関係ないではなく
今は過去ではないから、その時代の弱い自分は関係ないではなく、
その過去の自分の弱さを十分に受け入れることが
目の前にいるまだ弱い相手に対して、心からの共感を示すことができる「真の優しさ」を手に入れることができるのです。