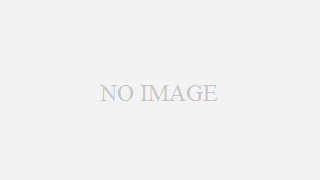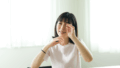コミュニケーションやカウンセリングの学びを深めるほど、「受容」という言葉の重要性に突き当たります。相手の話をしっかり聞き、受け止め、オウム返しをすることで「私はあなたの話をちゃんと聞いていますよ」と伝える。これは、人間関係の信頼を築き、コミュニケーションを円滑にする上で推奨される、極めて大切なスキルです。
ところが、実際に共感しようと努めても、いざ自分の意見と相手の意見が食い違うと、私たちは無意識のうちに「ジャッジ」してしまい、「それはおかしいでしょう?」と否定の言葉を挟んでしまうことがあります。自分と違うものに対して、どう受け止めたらいいのか、途端に難しくなるのです。
「ジャッジ」が引き起こす悪循環
私たちは、相手の意見が「正しいか間違っているか」「世間の常識からズレていないか」といったフィルターを通して話を聞いてしまいがちです。しかし、その時、大切なのは**「あくまでその人にはそう見えているんだね」**と、一旦、その人の認識をそのまま受け止めることです。合っているか間違っているかは一旦横に置き、「あなたはそう思っているんですね、とりあえず聞きますね」というスタンスを取る。
それでも、やはり私たちの心にはジャッジが入ってしまう。ジャッジすればするほど、相手の話は「くだらないこと」に聞こえたり、「なんでそんなことで悩んでいるんだ」と苛立ちを感じたりするようになります。「こうすればいいのに」と、一言挟みたくなる衝動に駆られる。しまいには、自分の考えと相手の話が一致しないことに疲弊し、話を聞くこと自体が苦痛になることもあります。
この時、私たちは、**「私はあなたの話をちゃんと聞いているのに、なぜあなたは私の意見を聞かないんだ?」**という、無意識の要求を相手に突きつけてしまっているのかもしれません。これでは、相手は「相談したら怒られた」と感じ、信頼関係は崩れてしまうでしょう。
「共感と同意の線引き」の難しさ
また、共感しようと意識するあまり、自分の意見を伝えることで相手を否定してしまうのではないか、と恐れてしまう側面もあります。十分な受容や共感ができていないと感じると、「ここで自分の意見を言ったら、結局この人も私を否定するのか」と捉えられるのではないかという恐怖が生まれるのです。
しかし、相手の気持ちを100%受け止めながらも、現実的な状況や本人の目指す理想を踏まえた上で、「この考え方だと、この先ちょっと困るかもしれないな」という場面は必ず出てきます。その時、単に「じゃあ、こうしましょう」と一方的に押し付けてしまっては、結局、相手は「受け入れられた」とは感じないでしょう。
共感と同意の線引きは、支援者にとって永遠のテーマです。相手の価値観や考え方を完全に受け入れることと、相手の望む未来のために建設的な視点を提供すること。この二つのバランスが、非常に難しいのです。
「気づき」を促す質問の力
では、どうすれば良いのでしょうか。
重要なのは、「自分と他人が違う」という事実を、心底から受け入れることです。あくまで自分は自分のことしかできないし、他人のことはコントロールできない。だから、他人の考え方も当然コントロールできるわけがなく、自分と一致しているはずがない。だから、ただただ相手の話を聞く。そこに「合ってる」「間違ってる」は必要ありません。
その上で、相手の感情を十分に受け止め、共感できたと感じた時、次のステップとして**「質問をぶつける」**という方法が有効です。
思い込みが強かったり、悩みやすかったり、人間関係がこじれやすい人は、往々にして**「自分が正しい」という正義感に囚われ、物事を一方向からしか見ていない**ことが多いものです。そのため、それ以外の視点を「正しくない」とジャッジしてしまいます。
だからこそ、私たちは「こんな考え方もあるよね」「こんな見方もできるよね」と、多角的な物事の見方を提示する、あるいは相手自身が気づけるような質問を投げかけることが理想的です。
「もし、その状況が違う角度から見えたとしたら、どう感じるだろう?」 「その行動をとることで、あなたにとって最終的にどんな結果がもたらされると思う?」 「あなたが本当に望んでいることは何だろう?」
このように、人に言われて「そうなのだ」と受け入れるのではなく、自ら「なるほど、そういう見方もできるのか」と気づくことで、相手は「押し付けられた」と感じることが減ります。そして、最終的に相手がどう思うか、どう行動するかは、彼ら自身が選択することです。
弱さを受け入れた先にある「真の優しさ」
私たちの力は決して万能ではありません。他人のことも、結果も、外部環境も、私たちの思い通りには変えられない。自分は自分のことしか直接的に影響を及ぼせないという意味では、私たちは「弱い」存在です。
しかし、その「弱さ」を受け入れ、自分がコントロールできる範囲に集中する覚悟ができた時、私たちは真の優しさを手に入れます。自分の不完全さを知っているからこそ、他者の不完全さをも丸ごと受け止め、「あなたはそうなんだね」と寄り添うことができる。
「ジャッジしない」ことは、単なるテクニックではありません。それは、自分の弱さを受け入れ、他者の多様性を尊重する、あなたの心の成熟がもたらす、真の優しさなのです。この優しさが、人間関係に深い信頼と、豊かな変化をもたらしていくでしょう。