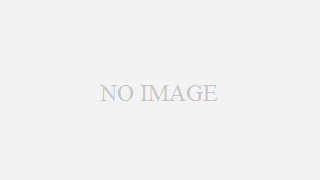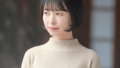自己啓発の世界では、
「抽象度を上げると問題が解決しやすくなる」という言葉をよく耳にします。
しかし、この「抽象度」という概念を日常生活にどう落とし込むのか、
多くの人が悩むのではないでしょうか。
今回は、私の具体的な経験を交えながら、
この抽象度を上げるという考え方が、
いかに私たちの問題解決能力を高めるかを解説します。
「抽象度」とは何か?食べ物で例えるなら
「抽象度」とは、物事をより大きな視点、広い概念で捉えることです。例としてよく使われるのが「食べ物」の例です。
- 具体的な例: カレーライス、うどん、チャーハン、そば
- 少し抽象度を上げる: うどんとそばは「麺類」、カレーライスとチャーハンは「ご飯物」
- さらに抽象度を上げる: これら全ては「食事」
このように、より抽象度を上げることで、
個別の具体的な違いに囚われず、
共通の大きな枠組みで物事を捉えることができます。
ただ・・・
実際の私たちの生活で直面する問題は、
食べ物のように単純ではありません。
私はこの抽象度が
自分の日常の問題と何が関係するのか
ずっと意味がわかりませんでした。
しかし、今日は以下言語化していきます。
日常生活での「抽象度」の壁:求人広告の担当者との確執
私自身、この「抽象度を上げる」という考え方を理解し、
実践するまでには時間がかかりました。
例えば、会社を経営する中で、スタッフの採用は避けて通れない課題です。
かつて、私は求人広告を出す際に、求人広告会社の担当者と相性がよくありませんでした。
私が求めている広告内容に対し、
担当者は「それでは人が集まりません」と意見をぶつけてくる。
もちろん、担当者もプロとしての意見を言っているわけですが、
当時の私は「出したい広告が出せないなら面倒だな。」
「(だから)できる限り求人広告を使いたくない」と無意識に考えていました。
場合によっては、「別の会社に求人広告を依頼しようか」とまで考えていました。
この状態は、まさに抽象度が低い状態でした。
つまり、「人を集める」という本来の目的からズレて、
「求人広告の担当者とのやり取りが嫌だから、求人広告を出したくない。」という
非常に具体的な部分に執着してしまっていたのです。
求人広告はあくまで「人を集めるためのツール」に過ぎません。
当然ですが、目的はそこにあるわけです。
しかし、そのツールを使うかどうかの判断を、
担当者との相性という個人的な感情に左右されてしまっていたわけです。
目的は人を集める事なので
本来、担当者との相性などどうでもいい。
しかし、ここに執着したことによって
抽象度が下がっていたのです。
つまり、人を集めるという目的のもと
集めればなんでもいい。・・・抽象度が高い
担当者と仲が悪いから、ここの会社は使えない・・・選択肢が1つなくなる、目的もズレている。抽象度が低い。
目的のズレに気づき、抽象度を上げる
幸いなことに、
私はこの時に自分の意識のズレに気づくことができました。
私の本来の目的は「人を集めること」であり、
求人広告はそのための手段の一つに過ぎない、
ということに立ち返ったのです。
この「人を集める」という目的に焦点を当てることで、
私の視野は一気に広がりました。
求人広告を使うにしても、担当者との個人的な感情は二の次になりました。
大切なのは、目的を達成するためにどうするか、です。
担当者と多少意見が合わなくても、
最終的に人が集まればそれで良い、と割り切ることができたのです。
さらに言えば、「人を集める」という目的であれば、
求人広告以外の方法も考えられます。
だって人を集めればいいのですから。
人材紹介サービスを利用する、SNSで告知する、知人の紹介を募るなど、
選択肢は無限に増えていきます。
このように、
目的を明確にし、抽象度を上げることで、
問題解決のためのアプローチが多角化し、選択肢が増え、問題が解決しやすくなりました。
具体化しすぎると見えなくなる「本来の目的」
抽象度が低い、つまり物事を具体的に見すぎると、
私たちはしばしば本来の目的を見失いがちです。
私の例で言えば、「人を集める」という目的があるにもかかわらず、
「求人広告の担当者と合わない」という手段の具体的な問題に囚われ、
結果的に「求人広告を使わない」という、
目的からズレた行動を取ろうとしていました。
私たちは日々の生活の中で、
目の前の具体的な事象や人間関係に振り回され、
本来の目的からズレたことをしていることに気づかないことがあります。
人間関係のこじれ、些細なトラブル、目の前の面倒な作業…
これら全てが、私たちの思考を具体レベルに固定し、
より本質的な解決策を見えなくさせてしまうのです。
抽象度を上げて、問題解決への道を拓く
問題を解決するためには、
意識的に抽象度を上げ、本来の目的を明確にすることが重要です。
目的が明確になれば、たとえ目の前の手段がうまくいかなくても、
別の手段を検討する柔軟性が生まれます。
また、人間関係のような感情が絡む問題であっても、
「本来の目的達成のためには、この関係性はどの程度重要なのか?」と
冷静に判断できるようになります。
たとえば、求人広告の担当者との関係に固執していたとしても、
「人を集める」という目的が最優先であれば、
担当者の交代を申し出ることも選択肢に入ります。
あるいは、たとえ気まずさを感じたとしても、
目的達成のためには割り切ってコミュニケーションを取ることもできるでしょう。
抽象度を上げるということは、
問題解決における視野を広げ、多様な選択肢を自分自身に与える行為です。
目の前の具体的な問題に囚われず、
一歩引いて、より大きな視点で物事を捉える習慣をつけることで、
私たちの問題解決能力は格段に向上するはずです。