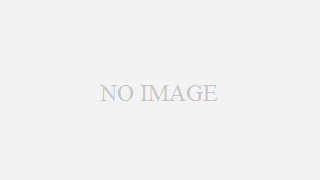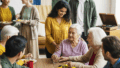アドラー心理学では、
真の幸福への道は「自立」にあると説きます。
この自立とは、単なる経済的な独立を指すのではなく、
人生の主語を「私」から「私たち」へと切り替えること。
つまり、誰かを愛し、
「私とあなた」で「私たち」となり、
その「私たち」の幸せのために私がどう貢献できるかを考えることだと説明しました。
しかし、ここで素朴な疑問が浮かびます。
「別に一人でもいいじゃないか。山にこもる人たちは幸せではないのか?」と。
「一人でいること」と「幸福感」
アドラー心理学は、
決して「一人で過ごすことが悪い」とか
「誰にも貢献していない人は不幸だ」と言っているのではありません。
そうではなく、「幸福感を感じにくい」と表現します。
なぜなら、人間は生まれつき「所属欲求」を持っており、
何らかの共同体に属したいと願う存在だからです。
そして、その所属の中で他者に貢献することで、
最も深く、持続的な幸福を感じるようにできているのです。
もちろん、自分を満たすだけでは幸せになれないわけではありません。
美味しいものを食べたり、好きなものを買ったりすれば、
一時的な喜びや満足感は得られます。
しかし、それは自分だけ満たした状態であり、
その影響は自分にしか及びません。
そのため、得られる幸福の大きさは限定的だと言えるでしょう。
社会の中で多くの人に貢献できることは、
多くの人の幸せに影響を及ぼします。
その結果、「私は貢献できた」という実感を得て、
それが自分自身を満たし、幸せに繋がるのです。
要するに、得られる幸福の大きさは無限大となるわけです。
エゴで貢献すると、なぜうまくいかないのか?
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
それは、他者への貢献を「エゴ」でやってしまうとうまくいかないということです。
表向きは貢献しているように見えても、
その動機が承認欲求を満たすためであったり、
他人との優劣比較で自分を良く見せるためであったりすると、
真の貢献感や幸福には繋がりません。
アドラー心理学における「健全な優越性の追求」とは、
他者と比べて自分が優位に立つことを目的とするのではなく、
自分自身の可能性を最大限に引き出し、より良い自分になろうとする向上心を指します。
エゴによる貢献は、この健全な追求から大きくズレてしまいます。
エゴで貢献しようとすると、なぜうまくいかないのでしょうか?
- 目的が「他者のコントロール」になるから: エゴによる貢献は、究極的には「相手に認められたい」「相手から評価されたい(承認欲求)」という欲求が根底にあります。これは、他者の感情や評価をコントロールしようとする試みであり、アドラー心理学の「課題の分離」に反します。他者はコントロールできない存在であるため、期待通りの反応が得られないと、不満や怒り、失望を感じ、貢献どころか関係を悪化させてしまうのです。
- 自己肯定感が不安定になるから: 他者からの承認だけを自己肯定感の源にしようとすると、それは非常に不安定なものになります。なぜなら、他人はやはりコントロールできないからです。他者の評価は移ろいやすく、常に他者の期待に応え続けなければならないというプレッシャーに繋がります。承認が得られなければ、途端に自己肯定感は揺らぎ、「自分には価値がない」と感じてしまう。これは、真の貢献感が与える揺るぎない自己肯定感とは対極にあります。
- 貢献が義務や負担になるから: 純粋な貢献ではなく、見返りを求めるエゴが混じると、貢献は「相手にやっているのに」という不満や、「これだけやったんだから」という計算を生みます。こうなると、貢献は喜びではなく、義務や負担に感じられるようになり、長続きしません。
結果が出なくても、貢献の姿勢を保つ
私たちは、自分のできることを精一杯やって貢献したとしても、
必ずしも望む結果が出るとは限りません。
なぜなら、結果は自分だけの力でコントロールできるものではなく、
外的要因も大きく影響するからです。
しかし、そこで執着したり、諦めたりする必要はありません。
うまくいかなかったことを経験として活かし、
「どうしたらもっと良い結果が出せるか」を考え、
自分のできることに集中し続けるのです。
つまり、「私を含めた私たちの幸せのために貢献する」という、
主語を「私たち」に切り替えた姿勢を保ち続けることが重要なのです。
自分のことを満たすだけでは得られない、
他者とのつながりの中での「貢献感」こそが、真の幸福の源泉です。
そして、その貢献は、エゴではなく純粋な共同体への意識から生まれるものであるときに、
最も大きな喜びと自己肯定感をもたらしてくれるのです。
要するに、自分を最大限幸福にしてくれるということになります。
自分が貢献しても、相手が感謝を伝えてくれなくても気にしない。
ちなみに、これは相手が感謝を伝えて来なくても
期待した反応をしなくても、気にしないということです。
なぜなら、相手はコントロールできないからです。
これはアドラー心理学における
「課題の分離」のところであります。
つまり、あなたが貢献や親切をしたとき、
相手がそれに対して感謝の気持ちを伝えるかどうかは相手の課題であり、
あなたがコントロールできる領域ではありません。
重要なのは、
あなたが「他者に貢献したい」「私たち(共同体)のために何かしたい」という
動機で行動したという事実、
そしてその貢献によって
あなた自身が「自分は価値ある存在だ」という貢献感を得られたことです。
※ざっくり言うと、相手が喜ぶためにやっているのではなく
自分が幸せになるために、私たちの幸せを考えて貢献しているだけだから、
相手が感謝を伝えてこなくても、どうでもいい。
目的は「わたし」が幸せになるための手段であるからと言えます。(でも、相手のことはどうでもいいにはなりません。相手を含めた私たちの幸せを考えて貢献するから)
相手の反応や評価に一喜一憂せず、
自分の行動の目的が、他者からの見返りや承認ではなく、純粋な貢献感にあるのであれば、
相手が感謝の言葉を述べなくても、
あなたの幸福感や自己肯定感が揺らぐことはありません。
「相手のために」という意識だけでなく、
「自分が幸せであるために他者に貢献する」という視点が、アドラー心理学における他者貢献の核心です。
多くの人は、「貢献」と聞くと自己犠牲や義務のように感じがちです。
しかし、アドラーはそうではありません。
他者に貢献することは、
自己肯定感の源であり、真の幸福感をもたらす唯一の方法だと説いています。
相手に何かを与えることで、
結果として「自分は誰かの役に立っている」「自分は共同体の一員として価値がある」という貢献感を内側から得られます。
この貢献感こそが、私たちの心を満たし、揺るぎない幸福感に繋がるのです。
つまり、
他者貢献は、相手のためだけでなく、
あなた自身の幸福のために不可欠な行動なのです。