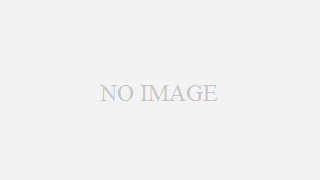「ありがとう」
口に出すことはできても、心からの感謝が伴わない。
そんな経験はありませんか?
私にとって、「感謝できない」ということは、
人生前半の大きなテーマでした。
表面的な言葉だけが虚しく響き、
心の中で「本当に感謝したいのに、なぜできないんだろう?」と
ずっと葛藤していました。
今振り返ると、その根底には
「他者は悪者だ(自分の人生を不幸にする)」という思い込み、前提がありました。
厄介なことに、この思い込みは無自覚であることが多く、
「まさか自分がそんな風に考えているなんて」と感じるかもしれません。
無自覚の自己防衛:他責という名の逃避
「他者は悪者だ」という思い込みがあったと書きましたが、
これは常に思っているわけではなく
どちらかと言えば、自分は好意的に見ていると思いこんでいました。
ただ、何か嫌なことが起こると、
反射的に誰かのせいにしていました。無自覚に。
自分の思い通りにならないのは環境のせい、
人間関係で不快な思いをしたときは相手が悪い。
そうやって責任を外部に転嫁することで、
短期的な心のダメージを軽減していたのだと思います。
これは自己肯定感が低いゆえに起こります。
なぜなら、問題の原因を自分にしてしまうと、自分が傷つくからです。
低い自己肯定感をさらにさげないように
無自覚に自分を守るために
※自己肯定感の低さがすべての悪循環を起こすということ。
「他人を敵にする」ことで
自分の人生の責任をその敵になすりつけることで
低い自己肯定感の自分を守ることができるということです。
しかし、これは当然ながら本質的な問題解決からの逃避に他なりません。
なぜなら、私たちがコントロールできるのは自分自身だけだからです。
問題の原因を他人や外部環境に求める限り、
私たちはその問題を自力で解決する力を手放すことになります。
これは、自分の人生の責任を放棄し、他人や環境に委ねるという行為に繋がります。
傷つきたくないという無意識の自己防衛が、私たちを無自覚の他責思考へと導くのです。
なぜ自己肯定感が低いと感謝できないか
ここまでの話を踏まえた上で、
なぜ、自己肯定感が低い人は感謝できないのか。
自分を守るために
他人のせいにする思考を続けていくことで
短期的に自分は傷つかなくていいですが
前述したように、自分で自分の問題を解決できなくなるので
自分の問題は他人や外部環境によってのみ解決されるという思考になります。無自覚に。
自分では何もできない人
つまり、「与えられる人」にならなければならなくなります。
「与えられる人」なので
与えられて当然の人になります。
結果、与えられても感謝しにくくなります。
話を戻しますが「与えられる人」である限り、
他者からの助けは当然の権利のように感じてしまいます。
まるで、子供が親に何かをしてもらうのが当たり前だと感じるように。
助けや好意を受け取っても、
「ああ、当然だ」と感じてしまい、
心からの感謝の気持ちは湧いてきません。
これは、感謝の気持ちが麻痺してしまっている状態と言えるでしょう。
低い自己肯定感だからこそ感謝できない
他者を悪者にして自分を正当化することは、
一時的に自己肯定感が高まるように見えるかもしれません。
しかし、その根底には
「自分には価値がない」
「自分は愛されるに値しない」といった低い自己肯定感が潜んでいます。
その低い自己肯定感を隠し、
これ以上傷つくことを恐れるあまり、
「だから他者が悪いんだ」という被害者の立場に身を置くことで、
辛うじて心のバランスを保とうとしているのです。
この状態で親切な行為を受けた場合
自分を守るために
「親切にされなきゃダメな自分ではない。」
自分はそんな能力は低くない。
余計なことをしやがって・・・と
プライドが邪魔したり
「頼んでもいないのに借りをつくってしまった」という
貸してほしいと頼んでいないのに
無理くり貸された本のようなストレスを感じたり
「自分が足りなかったせいで、この人の貴重な時間を使わせてしまった」と
自分を責めたり
このような心理が働いて
素直な感謝の気持ちを妨げてしまうのです。
過去の私から、今のあなたへ
過去の私は、「感謝できない」という苦しみの中で、もがき続けていました。
その根源には、無自覚の他責思考と、
それによって歪められた自己認識があったのです。
もし今、あなたが「感謝できない」と感じているなら、
一度立ち止まって、自分の思考の癖を振り返ってみてください。
もしかしたら、あなたの中にも、無自覚の「他者を悪者にする」思考が潜んでいるかもしれません。
この思考のパターンに気づき、手放していくことこそが、
心からの感謝を取り戻し、主体的な人生を歩むための第一歩となるはずです。