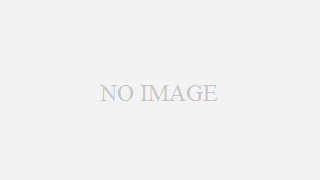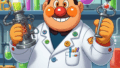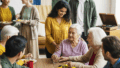私たちは皆、自分のことしかできなません。
他人の言動をコントロールすることはできません。
にもかかわらず、
「ああしてほしい」「こうしてほしい」「なぜしてくれないの?」と、
私たちは常に他人に期待を抱いてしまいます。
しかし、これらの期待は、
結局のところ他人の行動をコントロールしようとする試みに過ぎません。
なぜなら、他人の言動は、その他人にしかコントロールできないからです。
主体性こそが人生の境目
まさにこの点が、
スティーブン・コヴィーの『7つの習慣』の
第一の習慣「主体性を発揮する」に通じます。
自分の人生の責任は自分にあると自覚し、
他責にせず、他人に依存しない生き方を選ぶこと。
この主体的に生きる姿勢こそが、
ホーキング博士の意識レベルで200という臨界点(意識のマップにおける境界線)を
境目とすると言われます。
しかし、これは簡単なことではありません。
私たちは他人の目が気になったり、承認欲求を満たそうとしてしまったりするからです。
要するに執着してしまう。
誰かと自分を比べ、
上下関係や優劣に囚われてしまうと(執着してしまうと)、
この臨界点を超えるのは非常に難しくなります。
アドラー心理学「課題の分離」で自由になる
この「自分と他人を分ける」考え方は、
アドラー心理学にも深く根ざしています。
アドラーはこれを「課題の分離」と表現しました。
- 私たちの課題: 私たちがどう行動するか、どう感じるか、何を信じるか。
- 他人の課題: 他人がどう行動するか、どう感じるか、何を信じるか。
この二つは、明確に分離されているとアドラーは考えます。
例えば、あなたが誰かに親切にしても、
相手がそれに対して感謝するかどうかは相手の課題です。
あなたが相手に感謝してほしいと期待しても、
それは相手をコントロールしようとすることになり、
最終的にはフラストレーションを生むだけなのです。
コントロールできないからこそ「今、ここ」に集中する
他人の言動がコントロールできないからこそ、
私たちは以下の点に意識を向ける必要があります。
- 自分の課題に集中する: 相手がどう反応するかではなく、自分がどう行動したいか、どう貢献したいかに焦点を当てます。例えば、相手に感謝を期待するのではなく、「自分は相手に親切にしたい」という自分の行動に集中するのです。
- 期待を手放す: 相手への過度な期待は、失望や怒りの原因になります。相手は自分の期待通りには動かない、という事実を受け入れることが、心の平穏に繋がります。
- 相互尊重と相互信頼: 相手の選択や行動を尊重し、たとえ自分の期待と違っても、その人の自主性を信じることです。これが、健全な人間関係の基盤となります。
- 影響力を発揮する: コントロールはできませんが、自分の言動を通して相手に影響を与えることはできます。例えば、自分が率先して模範を示すことで、相手が自ら行動を変えるきっかけになる可能性はあります。しかし、それはあくまで「影響」であり、「強制」ではありません。
他人の言動をコントロールしようとする試みは、
エネルギーの消耗と人間関係の悪化を招くだけです。
自分の課題に集中し、相手の課題を尊重することで、
より自由で充実した人間関係を築くことができるでしょう。
だからこそ、今ここに集中し、自分のことに集中して生きることが大切なのです。
あなたの人生の主導権は、あなたが握っています。