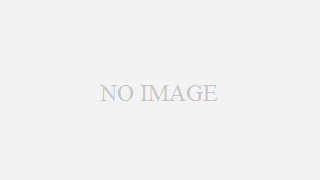前回のブログでは、
相手のコントロールできない言動に執着することの苦しさ、
それがまるで天気を変えようとするような無理難題であることをお伝えしました。
しかし、「そんなことは分かっているけれど、それができないから困っているんだよ」という声も聞こえてきそうです。
今回は、なぜ相手を「あるがまま」受け入れることが難しいのか、
その深層心理に迫ります。
結論から言えば、相手を受け入れることは、実はそれほど難しいことではありません。
ただ、それは自分自身を受け入れることができていることが前提です。
なぜなら、他者はしばしば、私たちの内面を映し出す鏡のような存在だからです。
相手は自分の映し鏡?自己否定が他者への不寛容を生む
もし、あなたが自分の本当の欲求に気づけていなかったり、
その欲求を満たすことを自分に許せていなかったりする場合、
目の前の相手を「あるがまま」に受け入れることは非常に困難になります。
例えば、「本当は分からないことは『分からない』と言って、誰かに頼りたい」という欲求が自分の中にあるとします。
しかし、
「自分は上司だから」
「年上だから」
「しっかり者でいなければならない」
という思い込みがあると、その欲求を抑圧してしまいます。
これは、そういう甘えたいという本当の自分に、自分がOKしない
つまり、自分が本当の自分をあるがまま受け入れることができていなくて、
嘘の自分を頑張ってやっている状態ですね。
そんな時、目の前で部下が何度も同じ質問をしてきたり、
自分で調べもせずにすぐに「教えてください」と甘えてくるような態度を見ると、
どう感じるでしょうか?
おそらく、強いイライラや不満を感じ、
「もっと自分で考えろ!」「しっかりしてくれ!」という感情が湧き上がってくるでしょう。
これは、相手の行動がどうこうなのではなく、
相手の行動を通して、あなたが自分自身に許していない
「甘えたい」や「頼りたい」本当の自分を受け入れることができていないだけなのです。
つまり、相手の姿は、
あなたが抑圧している「本当の欲求」を映し出しているだけと言えるのです。
自分への不許可が、他人への不寛容に繋がるメカニズム
人間は、根源的に自分が一番大切です。
だからこそ、まず自分自身の欲求をきちんと満たしてあげること。
それを通して、心が満たされ、余裕が生まれることで、
初めて他者に対しても寛容な気持ちを持つことができるのです。
上記の例で言えば、
まず自分自身に対して「誰かに甘えてもいい」「分からないことは人に聞いてもいい」という許可を与えることが大切です。
「自分で何でもかんでもやらなければならない」「常に完璧でなければならない」という思い込みは、多くの場合、幼い頃からの経験によって植え付けられた「自分ルール」に過ぎません。
この自分ルールに縛られていると、
そのルールから逸脱する他人を見た時に、
「この人はこうあるべきだ」という無意識のジャッジが働き、
その人を許せなくなってしまうのです。
これが、「相手をあるがままに受け入れられない」状態の正体です。
相手への苛立ちこそ、自分を知るチャンス
逆に言えば、私たちが相手の言動に強い不満や苛立ちを感じる時、
それは自分自身の内面に目を向ける絶好の機会を与えてくれているとも言えます。
「なぜ、私はこの人のこの行動にこんなに腹が立つんだろう?」と自問自答することで、
自分が無意識に抱えている「〜であるべき」というルールや、
抑圧している「本当の欲求」に気づくことができるのです。
そして、その自分ルールを手放し、
自分の本当の欲求を満たしてあげることで、
不思議なことに、相手の行動も気にならなくなっていくことがあります。
なぜなら、相手の行動が、
もはや自分の内面の葛藤を映し出すものではなくなるからです。
相手は、時に私たちにとって、
自分自身を深く理解するための鏡となります。
相手への不寛容さに気づいた時、
それは自分の中にあるルールや抑圧された欲求に気づき、手放すチャンス。
「相手をあるがままに受け入れる」とは、
まず「自分自身をあるがままに受け入れる」ことから始まるのです。