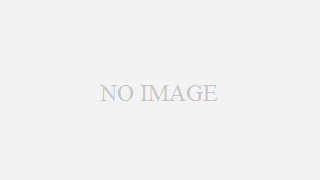小学校の頃の私は、ちょっと変わった生徒でした。
体調が悪くても、素直に「保健室に行きたい」と言えなかったのです。
その代わりに、わざとらしく体調が悪そうな素振りを見せ、
先生から声をかけてもらうのをひたすら待っていました。
今思えば、先生も授業で手一杯。
30~40人もの生徒がいれば、
一人ひとりの微妙な変化に気づくのは至難の業です。
それでも私は、なかなか気づいてくれない先生に業を煮やし、
大げさに机に突っ伏して寝てみたり、
露骨に顔をしかめてみたり。
国語の音読の時間には、わざと小さな声で読んでみたり…。
あの時の私は、先生に「いつもと違うぞ」と気づいてもらい、
「保健室に行ってきなさい」の一言を待つ、
典型的なかまってちゃんでした。
「言ってくれない」のは誰のせい?
今振り返ると、自分の「言えない」という課題を棚に上げ、
私が体調を崩したのは「先生が保健室に行けと言ってくれないからだ」と、
まるで責任を転嫁しているようでした。
「どうして言ってくれなかったんですか?」と
心の中で問いかけ、先生が忙しそうにしていたというもっともらしい理由を用意していましたが、
本音はただ、先生の気を引きたかっただけなのです。
極端な話、あの頃の私は、
体調不良さえも「かまってほしい」という欲求を満たすための
手段だったのではないかと疑うほどです。
なぜ、素直に「具合が悪い」と言えなかったのか?
この経験から痛感するのは、
「具合が悪いなら、具合が悪いと言えばいいだけなのに、なぜそれができなかったのか?」という疑問です。
本当の自分の気持ちを素直に表現できないのは、一体なぜなのでしょうか。
具合が悪いという事実は、
ただそれだけで良いはずなのに。
私たちは、いつの間にか自分を自分で満たすことを諦め、
他人を使ってその空虚感を埋めようとしてしまいます。
これは、言い換えれば、
自分で自分を満たす権利を放棄していることと同じです。
自分で唯一コントロールできるはずの自分自身を、他人に委ねてしまう。
他者への依存が奪う、人生を変える力
一見、人に頼ることは楽に見えるかもしれません。
会議で発言しなければ批判されるリスクはありませんし、
自信がない時は周りの意見に同調しておけば、
自分の評価が下がることもありません。
しかし、そういった受け身の姿勢は、
自分の力で人生を切り開いていく力を徐々に奪っていきます。
他者に依存する生き方は、自己肯定感を低下させ、
「自分の人生は誰かの支配下にあるのではないか」という無力感を覚えやすくなります。
そして、本当に変えたいと思った時でさえ、
その力を失ってしまうのです。
人に委ねることは、ある種の楽さをもたらしますが、
それは同時に、自分の人生に対する責任を手放すことでもあります。
「〜のせいだ」と他人や環境のせいにすることで、
自分自身は変わる努力をしなくても済むからです。
しかし、それでは根本的な問題は何も解決しません。
自分の人生を変えるためには、
結局のところ、自分自身が変わるしかないのです。
批判を恐れず、自分を貫く勇気
だからこそ、他人に叩かれようが批判されようが、自分が信じたことを貫く勇気が大切なのです。
(これがアンパンマンの世界観の「愛と勇気」の「勇気」だと私は考えています。否定してくる人はばいきんまんになるかと思います。)
自分の気持ちを素直に表現すること、
自分の意見を臆せずに言うこと。
それは、自分自身を大切にし、自分の人生の主導権を取り戻すための第一歩です。
小学校時代の私のように、
「言えない」という殻に閉じこもっていては、
いつまで経っても自分の本当の気持ちは誰にも伝わりません。
そして、満たされない思いを抱えたまま、
生きづらさを感じ続けることになるでしょう。
自分の人生を生きるためには、
まず、「言えない自分」に気づき、そこから抜け出す勇気を持つこと。
そして、他人に委ねるのではなく、自分で自分を満たすことを意識すること。
批判を恐れず、ありのままの自分を表現することこそが、
自己肯定感を高め、自分らしい人生を歩むための、最も大切な一歩なのです。
(この他者に批判されることを受け入れながら、それでも自分を大切にすることを貫くことこそが、「嫌われる勇気」)